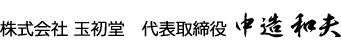文化元年(1804年)中造屋九右衛門が広島で雑貨卸商の「のれん」をあげ、その後、堺で薬種商を営み、高級線
香の製造卸売りを始めました。江戸末期から明治への大転換、大正デモクラシー、関東大震災、昭和初期の世界大恐慌、第二次世界大戦、戦後の不況から職人不足の高度成長期、そして、現在の厳しい景況へと歩みを進め、現在に至ります。その折々の当主は様々な局面で苦労を強いられ、有用な訓戒を家訓として残しました。
| 「細く長く」 |
|---|
| 商売は継続、永続を旨とします。拡大や多角化を拒み、本業に徹せよと言う意味です。大阪では「商売は牛のよだれ」と言って、長く続けるものだと表現しています。
|
| 「店(たな)は借り物」 |
| 企業の私物化を戒めています。金銭面でも公私の区別をしっかり付けて、社業に邁進するようにと言う意味です。前の代から借り受けた店を次の代に貸す、これを代々繰り返します。借りたときより、きれいにして次の代に貸すのです。
|
| 「出ん得」 |
|---|
| これは祖母から学びました。休みの日は無目的に外出しないほうが良いと言います。なぜなら、無駄なお金を使ってしまう危険があるからです。大阪弁で「出ん方が得やで。」これを縮めた言葉です。
|
| 「金貸さず」 |
|---|
| 金銭の貸し借りは人間関係を壊すだけでなく、自分の生活もだめにします。貸す時は神様のように崇められても、いざ返済を迫ろうものなら、今度は悪魔のように思われてしまうのです。
|
| 「浮利追わず」 |
|---|
| ギャンブルや宝くじなど、労働以外で得る金銭には価値が無いと考えます。商売を志す者は一攫千金を夢見てはならないのです。一度、そんな金銭を手にすると目が曇ってしまうので、株式への投資も禁じられています。
|
| 「判つかず」 |
|---|
| 絶対に保証人としての印鑑を押してならないと言われています。簡単な行為ですが、それから発生する責任は巨大です。その保証を受けた人の一挙手一投足を監視できるのなら構わないのですが、無理な話です。もし、判をつく必要があるならばそれに見合うお金を用意しておかねばなりません。
|
| 「役就かず」 |
|---|
| 人のお役に立つ役目はたくさんあります。しかし、それが自分の仕事のようになってしまってはいけません。社業に徹するのが基本です。しかも、役に就いて年月が経つと、次第に上の役職になって行きます。ここで「自分は偉い」と錯覚する危険が出てきます。自分の勉強になるかどうか、時間を取られ過ぎないか、これも役に就くかどうかの判断基準でしょう。
|
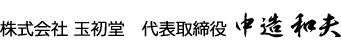 |
|